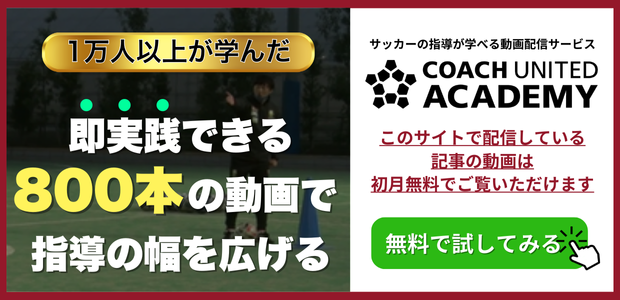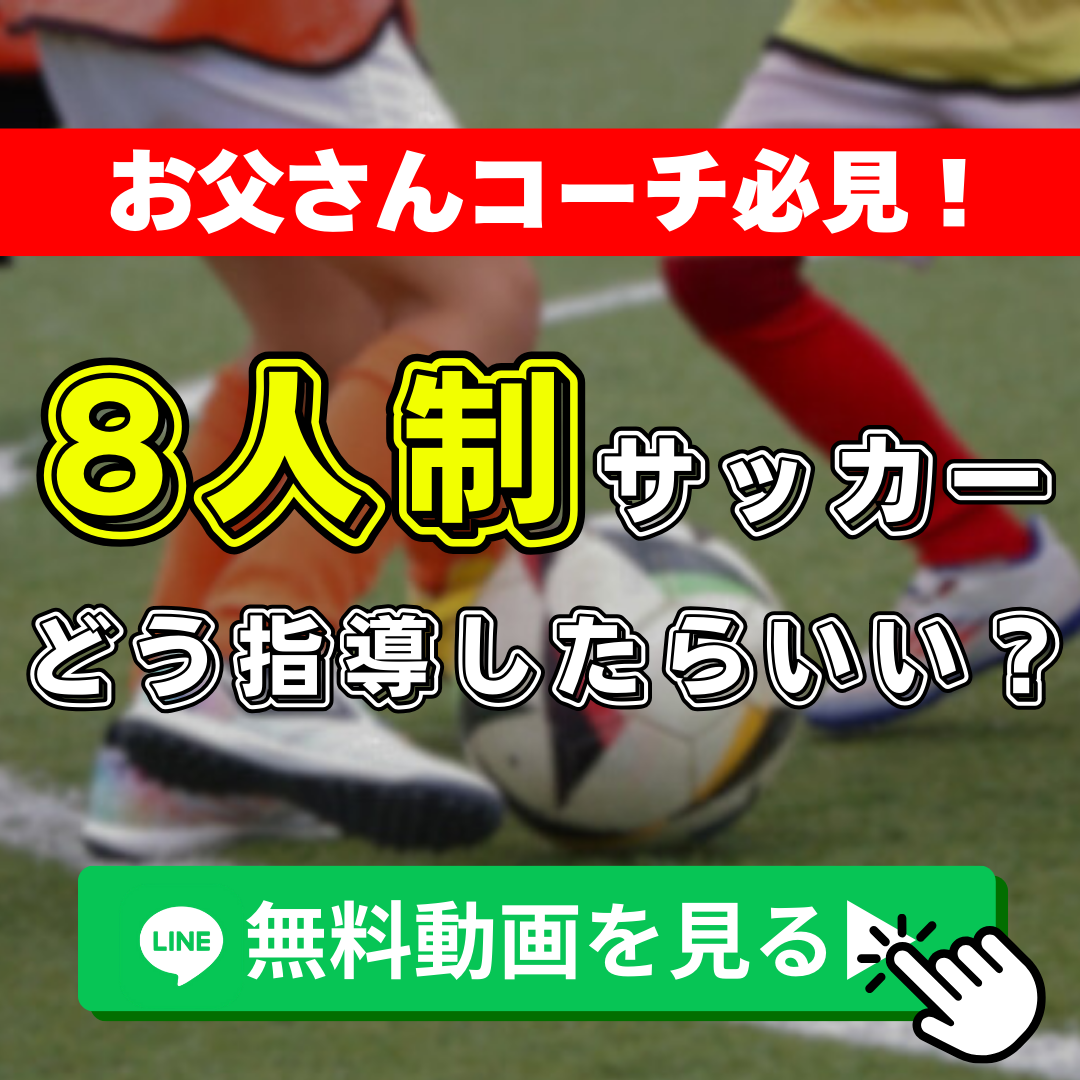07.22.2025
ペップに憧れて勘違いした指導者たち。サッカーの本質を見失わないトレーニングの基本とは?
サッカーの指導が学べる動画配信サービス「COACH UNITED ACADEMY」では、ヨーロッパなどにおける最先端の指導理論なども配信中だ。
今回は、ドイツを中心に指導者として、またジャーナリストとしても活躍する中野吉之伴氏に、「サッカーの基本を正しく身につけるトレーニングデザイン」について解説いただいた。
前編の「ヨーロッパにおけるサッカーの基本と解釈とは?」につづき後編では「サッカーの基本をどのようにトレーニングに落とし込むか」についてお届けする。(文・中野吉之伴)
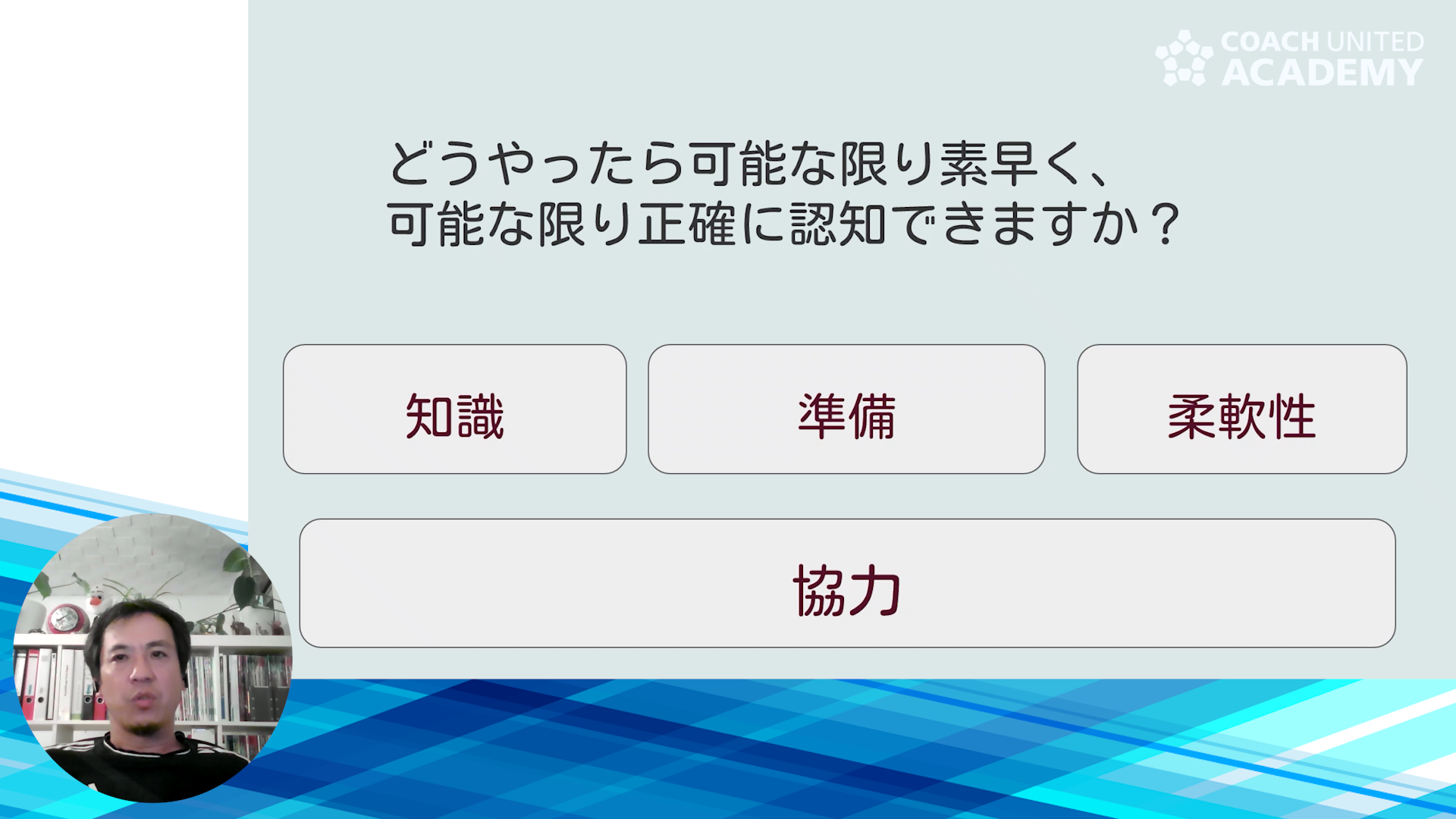
認知-判断-決断-実践
日常においても、サッカーのピッチにおいても、僕らはこうした《思考プロセス》を介して物事をとらえ、行動に移している。特定の状況下における特定のアクションを正確に行うだけでは、サッカーの試合で有効なプレーを連続で行うことは難しい。

刻一刻と状況が変わる中で、瞬時に周囲をスキャンし、どんな選択肢があるかを見つけ出し、どの決断がより効果的で、それをどのように実践に結びつけるかを、育成年代から継続的に取り組むことが必須条件としてあげられる。
脳内処理能力の必要性が高まってきている
ドイツサッカー界で認知に関する注目が高まりだしたのが、2015年ころからだろうか。ドイツサッカー連盟とドイツプロコーチ連盟の共催で行われる国際コーチ会議では、毎年のように認知に関する講義やトレーニングデモンストレーションがあったものだ。指導者向け雑誌のFussballtrainingでも認知に関する情報が頻繁に取り上げられ、グラスルーツの指導現場にも、明確な変化が見られるようになってきた。
認知スピードアップと判断・決断精度のアップのためにと、様々な脳トレを組み合わせたトレーニング理論が生まれたり、いかに最適に脳に負荷をかけて、脳内キャパシティをアップさせるかを考える指導者が増えてきたのは、まさに時代の流れ。
加えて、そうした脳内処理能力の必要性が、トップレベルにおいて高まってきているという背景がある。
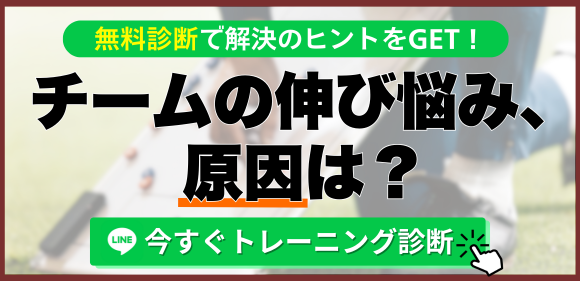
トップレベルのトレーニングは"ミーティングルーム"で行われている
昨年の国際コーチ会議にゲスト登壇した元リバープール監督のユルゲン・クロップがこんな話をしていた。司会から「全てのトレーニングで100%出し続けるためにどうするのが望ましいのでしょうか?」という質問に対する答えだった。
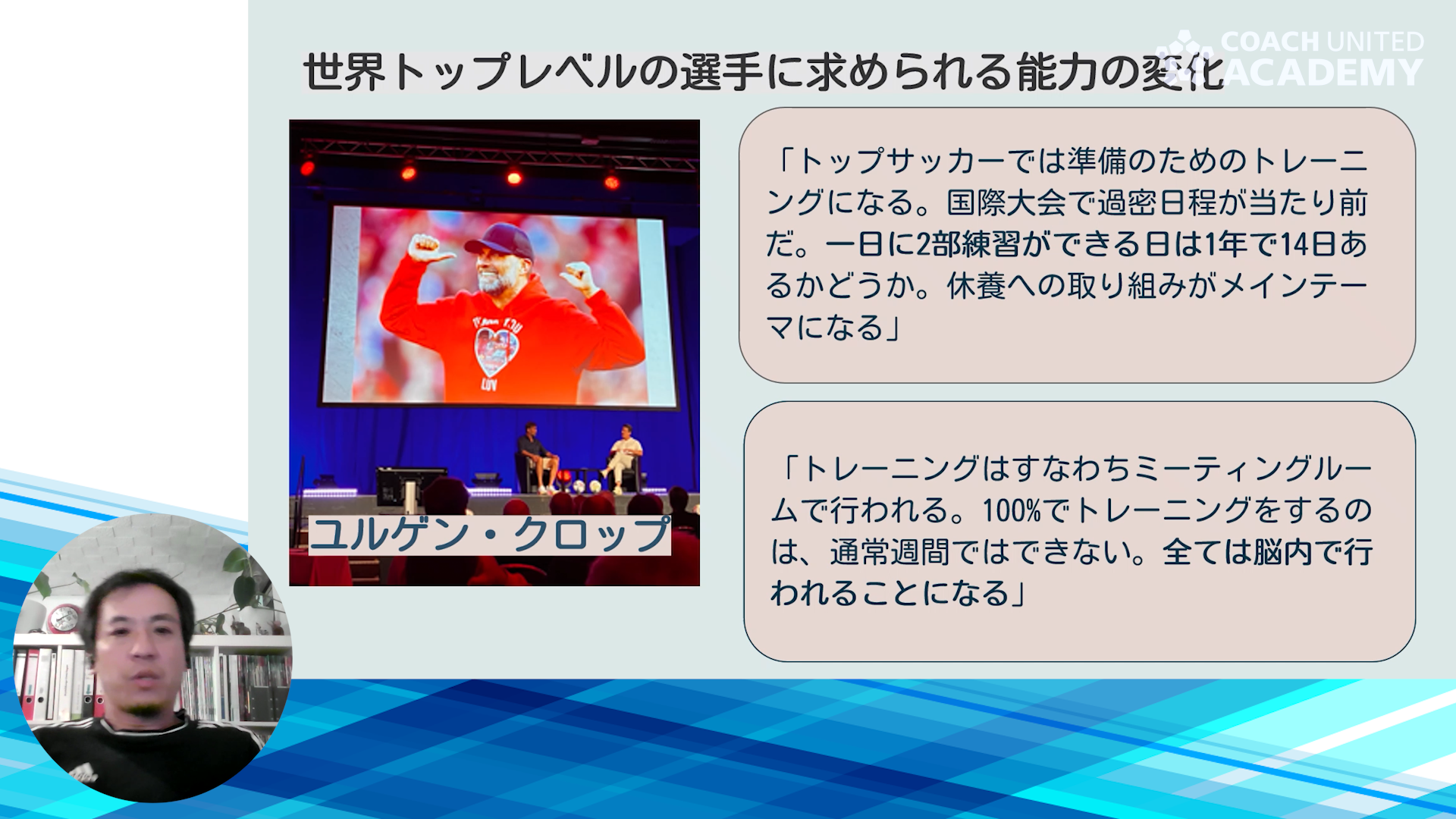
クロップ「トップレベルのクラブでは、ほぼすべてが準備のためのトレーニングになる。国際大会における過密日程は当たり前だ。一日に2部練習ができる日は1年で14日あるかどうかというレベルなんだ。リバープールでは日曜日と水曜日に試合がある前提でスケジュールが決まっていく。休養への取り組みがメインテーマだ。そのためトレーニングはすなわちミーティングルームで行われることになるんだ。100%でトレーニングをするのは、通常週間ではできない。全ては脳内で行われることになる。そして多くのことは普段通りに試合に向けて取り組むことになる」
世界トップレベルの選手はビデオ分析の映像を見て、監督やコーチの指示を聞いて、脳内に明確なイメージとしてインプットして、それを実際にグラウンドで披露できなければならない。試合で上手くいかないことがあったから、トレーニングで調整して、次の試合ではうまくいくように改善したい、ということがそもそもできない。それだけの戦術理解、ゲームインテリジェンス、状況認知能力、判断処理能力が備わっていなければならないのだ。
「複雑=良い練習」ではないという落とし穴
もちろん状況認知能力や判断処理能力が高まれば高まるほど、サッカーのプレーが自然とうまくなることはなく、体の扱い方、スキルの使い分けなど、それぞれに取り組むべきことだってたくさんある。ただ、一つ一つをバラバラに扱うのではなく、あくまでもサッカーの枠の中でアプローチできるようにするのが、トレーニングにおいてとても大切になる。
ドイツにおいても脳トレが流行っていたころは、トレーニング内容を複雑にすればするほどいいと勘違いする指導者も多くいた。特にペップ・グアルディオラやユリアン・ナーゲルスマンに憧れる若い指導者は、卓上のコマのように選手を動かそうとして、そうした習慣で育った選手たちは自己決定力、自己修正力、セルフモチベート力の欠如が見られるようになってしまった。
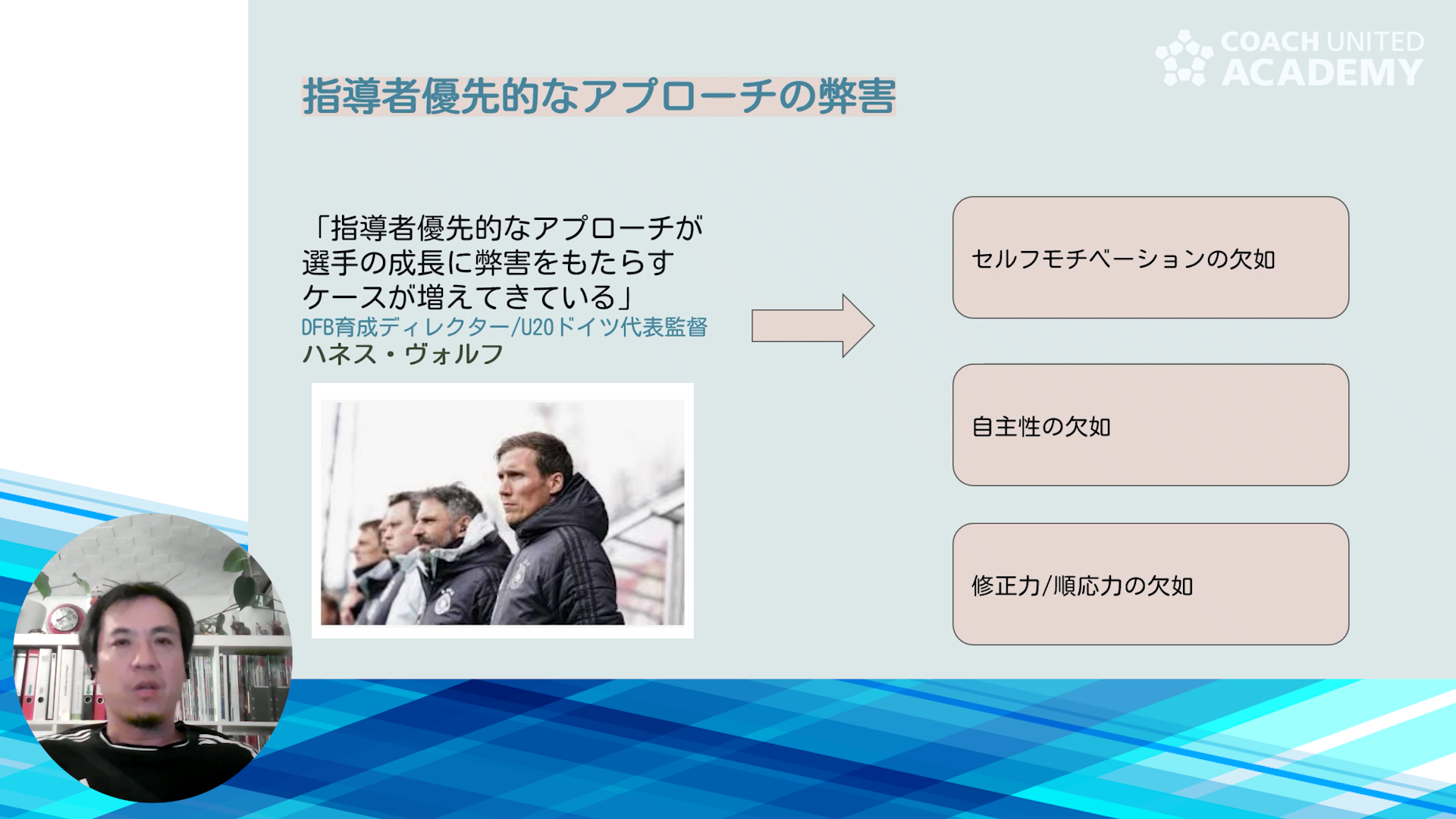
どんなトレーニングでも、どんな理論でも、本質の部分を間違えると、願うような効果が生まれることはない。
そして忘れてはいけない最も大事なことは、子どもたちは何がしたくてグラウンドに集まってきているか、だ。
サッカーをしたくて目を輝かせてグラウンドに来る子どもたちが、同じような、あるいはもっと輝かせた目とともに家路につけるかどうかがを、僕らは考え続けなければならない。サッカーをしたくてグラウンドに来たのに、サッカーができずに帰るのは、よくないのだ。

サッカーのトレーニングはサッカーが行われなければならない
うまくなるためにはしょうがないなんてことでもない。サッカーのトレーニングでは、サッカーが行われなければならないのだ。大人の感覚で15分前後なんとなく2チームに分けて紅白戦をして、それでオッケーというわけでもない。
15分だろうが、30分だろうが、人数設定とグラウンドサイズが適切でないと、ほとんどボールを触ることなくゲームが終わってしまう子どもがたくさんいるのだ。
何度もボールに触れて、何度も失敗をして、何度も悔しい思いをしながらも、また何度もチャレンジができるような環境をトレーニングから積極的に作っていくことこそが、サッカートレーニングの基本だ。
枝葉を茂らすためには、どっしりとした根と幹が育まれなければならない。

「COACH UNITED ACADEMY」で配信する中野氏の動画では、具体的にどのように日常のトレーニングに落とし込んでいくのか実際のメニューなども詳しく紹介している。ぜひ、詳細は動画を参考にしていただきたい。
【講師】中野吉之伴/
サッカー指導者・ジャーナリスト。大学卒業とともにドイツへ渡り20年以上在住。ドイツサッカー連盟公認A級ライセンスを保持し、元ブンデスリーガクラブ・フライブルガーFCをはじめ、数々のクラブで指導経験を持つ育成年代のスペシャリスト。現在はSVホッホドルフU17監督を務める。著書に「ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする」や「3年間ホケツだった僕がドイツでサッカー指導者になった話」などがある。
取材・文 中野吉之伴